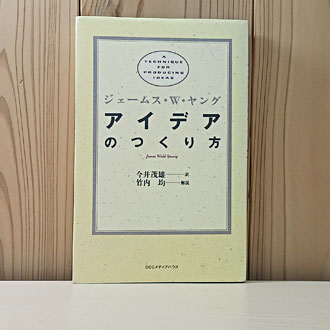アイデアの製造過程はひとつの流れ作業であるということ
デザインの仕事をしていると、アイデアの枯渇に苦しむ瞬間や何日ものあいだ何ひとつ思い浮かばない時期がある。
「一体、アイデアはどのようにして生まれるのだろう?」日頃から多くの情報に触れて疑問を持ちながら、調べて知識を増やすことがベースにあることは違いないのだが。
そんなチョットした疑問が、アイデアやひらめきに関する書籍を調べ始めるきっかけになった。
本書「アイデアのつくり方」を知るきっかけとなったのは、先行して読んでいた同出版社の「アイデアのヒント/ジャック・フォスター著」で紹介されており、薄い書籍ながら「アイデアを生み出す上での真髄」のようなものが書かれてあることを知り、すぐさま書店へ走り購入した。
本書を手に取った第一印象は「薄すぎる」ということだろう。一般的な新書の厚さに近いが、ハードカバーを採用しているため内容自体はもっと少ない。
実際、本書の構成は目次にはじまり、まえがきやあいさつ、本文、竹内均氏による解説およびあとがきという構成になっているので、本文のみでは約50ページ弱しかなく1時間もあれば通読できてしまう。
アイデアのつくり方という一見複雑なテーマながら、その短い文章の中に広告制作やデザインのアイデアを生み出すヒントが凝縮されている。
著者であるジェームス・W・ヤングにより、本来は英語で書かれた書籍を無理に日本訳している箇所があり、自分の理解力の悪さからか素直に文章が入ってこず何度か読み返す場面もあった。
本書の中でヤング氏は、アイデアを手に入れることにも公式があり、それはまるでフォード車を作り上げるのと同じような工程であるとする。
大切なことは、まず原理を識りその方法を知ること。
アイデアは既存の要素の新しい組み合わせであること。そして、その才能は事物の関連性を見つけ出す才能が大切であるという原理。
たとえ既存の要素が存在しても、その関連性に気づくことがなければ組み合わせることができない。
一見まったく関連性がなさそうな要素でも、修錬を積むことでその関連性を見出すことができるという。
アイデアを生み出す具体的な流れは5段階。
資料の収集からはじまり、咀嚼、無の状態になる、アイデアの誕生、具体化させ展開と進む。これらを一足飛びに行わず、必ずそれぞれの段階を終えて次へ進まなければならない。
一瞬にして頭にイメージが浮かんだ印象的な一文がある。
「一つの広告を構成するということはつまり私たちが住んでいるこの万華鏡的世界に一つの新しいパターンを構成するということである。」
少し角度を変えるだけで幾千通りもの新たな組み合わせを生み出す万華鏡の世界に例え、無数にあるパターンの中で新たな組み合わせを見つけることが広告であるとする。
無からは何も生まれない。
ノーベル賞を受賞するような化学者でも、先人の知恵や努力があるからこそ新たな組み合わせによる発見が生まれる。
デザインにおいて最も時間を要する場面は様々な資料の内容を咀嚼して吐き出す作業であるため、この場面を妥協して簡単に済ませると内容が薄く誰にも伝わらないデザインになる。
本書を読むことでより具体的に掘り下げて考えることができた。
本書は発想やひらめきなど日常的にアイデアを必要とする人たちだけでなく、物事の捉え方や考え方の一助となるでしょう。